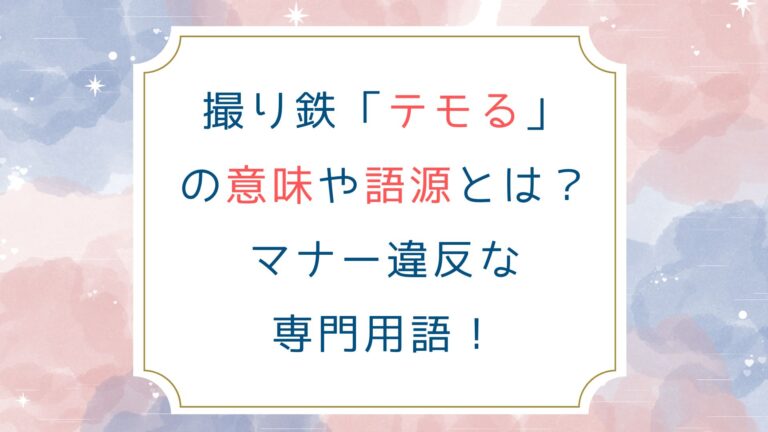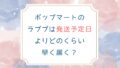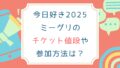近年、鉄道車両や鉄道風景の写真撮影を趣味とする鉄道ファン「撮り鉄」の撮影時のマナー違反な行動に批判が相次いでいます。
問題行動が取り上げられる中で「テモる」という言葉が聞こえてきますが、一体どんな意味なんだろう?と思った方も多いですよね。
そこで今回は以下の内容で記事をまとめたので、ぜひ最後までご覧ください!
▶撮り鉄「テモる」の意味
▶撮り鉄が問題視される理由
▶その他の撮り鉄専門用語・俗語の意味
▶撮り鉄以外の鉄道ファンの種類
撮り鉄「テモる」の意味
得体の知れない集合生命体っぽくなった撮り鉄まだ凄い pic.twitter.com/4zGfHV10KY
— イエス・キリスト (@JOJOkirst) July 15, 2025
さっそく、撮り鉄「テモる」の意味を見ていきましょう!
つまり、「テモる」とは撮り鉄による列車の運行妨害行為の一つとして使われています。
▶「撮り鉄」とは
鉄道車両や列車の写真撮影を趣味とする鉄道ファンのこと
「撮り鉄」とは鉄道車両や列車の写真撮影を趣味とする鉄道ファンで、その熱中のあまり線路内に入り、列車を止めてしまう事件も時折起こっています。
この言葉は特に近年、撮り鉄の迷惑行為やトラブルが社会問題となっていることから注目されています。
「テモる」の語源は?
はっきりとはわかっていませんが、「テモる」の語源は以下のように考えられています。
・一説には、「手を止める」や「列車(train)を止める」という意味合いから、短縮や変形によって「テモる」となった可能性があること。
・撮り鉄の周囲で使われる他のスラング同様、語感や分かりやすさを重視して作られたもので、正式な言葉ではなく俗語として自然発生的に生まれたもの。
「テモる」は独立した行為を示す俗語として使われています。
具体的な語源の説明は明確な資料が少なく、SNSや現場の鉄道ファンの間での口語的表現として自然発生して広まったものと推察されます。
撮り鉄が問題視される理由
撮り鉄が問題視される主な理由は、鉄道の安全や運行に関わる深刻な迷惑行為を引き起こすからです。
具体的には以下のような点が挙げられます。
1.線路内への立ち入り
撮影のために線路内に侵入し、列車の運行を妨げる行為が何度も繰り返されており、そのたびに列車の緊急停止や運転見合わせ、遅延が発生しています。
たとえば、2025年6月15日には宮城県名取市の館腰駅~岩沼駅間で撮り鉄が線路に入り込み、臨時寝台列車「カシオペア」の運転を39分間止め、約1100人に影響が出る事故がありました。
撮り鉄の安全の軽視と、理想的な写真を求める執着が背景にあります。
2.撮影目的の危険行為による事故リスク
線路内立ち入りや線路設備(ロープなど)を破損する行為は非常に危険で、時に事故や列車との接触事故にもつながっています。
過去には撮り鉄が書類送検されたり逮捕された例もあります。
3.運行妨害による社会的影響
多くの乗客が影響を受ける運転見合わせや遅延が発生し、公共交通の円滑な運営が阻害されること。
また、列車を止める行為は鉄道営業法違反だけでなく、威力業務妨害罪に問われることもあります。
4.マナー違反やトラブルの多発
撮影場所での混雑による地域住民や他の利用者とのトラブルが社会問題化しています。
こうした迷惑行為は撮り鉄全体のイメージダウンにつながっています。
5.SNSなどによる承認欲求の高まり
希少車両や特別な列車の写真を撮るために、危険な行為や無理な場所取りを強行しやすいという背景があります。
このように、安全面と社会的影響の観点から撮り鉄の迷惑行為は厳しく問題視されています。
その他の撮り鉄専門用語・俗語の意味
撮り鉄の専門用語・俗語には多くの独特な言葉が存在し、撮影や鉄道にまつわる状況を簡潔に表現しています。
代表的な用語のいくつかを以下に挙げます。
| 用語 | 意味・説明 |
|---|---|
| ウヤ | 運休。列車の運転休止のこと。元は国鉄時代の鉄道電報用語。例:「今日は狙いのカモレがウヤだ」=貨物列車が運休。 |
| カモレ | 貨物列車のこと。略語で親しみを込めて使われる。 |
| カブる(カブり) | 狙っている列車の前後を別の列車が被る(被ってしまう)こと。撮影の妨げになる。 |
| カマ | 機関車の俗称。もともとは蒸気機関車の釜が由来。 |
| ネタガマ | 特定の希少な機関車や原色機関車のこと。 |
| 廃回 | 廃車回送の略称。解体のために工場へ向かう列車。 |
| はえたたき | 線路脇の電柱の通称。形がハエたたきに似ていることから。撮影時には隠す工夫がされることも。 |
| 歯ヌケ | 貨物列車のコンテナが途中で積まれていない状態のこと。 |
| ひがはす | 東北本線の有名な撮影地の一つ。 |
| 激パ(げきぱ) | 撮影地に多くの撮り鉄が集まり混雑している状態。 |
| キャパクラ | 撮影場所の収容人数(キャパシティ)を超えて混雑していること。 |
| サイレント引退 | 鉄道車両が事前告知なしに静かに引退(運転終了)すること。過剰な撮り鉄の集まりを避けるために行われることがある。 |
| ジッセ | 次世代の若い撮り鉄(十代くらい)を指す言葉。 |
| シテン | 試運転の略。国鉄時代の電報略号。 |
| 地雷鉄(じらいてつ) | 他人に迷惑をかけるような問題のある鉄道ファン。主観的な使われ方が多い。 |
| バリ順 | 「バリバリの順光」の略。列車の進行方向に対し日光が順光で撮影条件が良い状態。 |
| ケツ撃ち | 列車のお尻(最後尾)を後ろから撮影すること。 |
| 串パン | 電柱や架線柱が列車の写真にかかってしまう失敗構図。 |
| パン人 | 鉄道趣味者でない一般人のこと。 |
| 雛壇(ひなだん) | 撮影者が多いときに全員が見やすいように前から高さがつけられた配置のこと。 |
これらは撮り鉄の会話やSNS、撮影現場でよく使われる言葉で、理解しておくことで撮り鉄仲間とのコミュニケーションや撮影状況の把握が容易になります。
撮り鉄以外の鉄道ファンの種類
撮り鉄以外の鉄道ファンの種類は非常に多く、多様な楽しみ方や関心分野に応じて「〇〇鉄」という形で細かく分類されています。
主な種類を以下にまとめます。
| 種類名 | 説明・特徴 |
|---|---|
| 乗り鉄 | 実際に列車に乗って旅を楽しむタイプ。鉄道の路線や乗車体験を重視する。 |
| 音鉄(録り鉄) | 電車の走行音や駅の発車メロディ、車内アナウンスなど鉄道に関わる音を録音・収集し楽しむ。 |
| 車輌鉄 | 車両の構造や性能、パンタグラフ、連結器などの機器や内装、外装の研究や観察を好む。 |
| 模型鉄 | 鉄道模型の制作やコレクション、走行を楽しむ。 |
| 収集鉄 | 切符や鉄道グッズ、不要になった備品などを集めるコレクタータイプ。 |
| 時刻表鉄 | 鉄道の時刻表を読み込み、ダイヤの分析や研究を楽しむ。 |
| 駅鉄 | 駅そのもの(構造や設備、駅名の由来)に興味を持ち、訪問や研究を行う。 |
| 廃線鉄 | 廃線となった路線を訪れたり、歴史を辿ったりする。 |
| 保安鉄 | 踏切や信号、ポイントなどの安全設備に関心を持つ。 |
| 歴史鉄 | 鉄道の歴史や変遷を研究・追求。 |
| 駅弁鉄 | 駅弁(駅で販売される弁当)を食べたり、包み紙を集めたりする食文化的な楽しみ方を持つ。 |
| 会社鉄 | 鉄道会社自体や経営状況、株式などに興味を持つタイプ。 |
| 法規鉄 | 鉄道の法律や規則を研究する人。 |
| 架空鉄 | 地図上に架空の路線を作成して楽しむ創作的なファン。 |
| ゲーム鉄 | 鉄道関連のゲーム(例:電車でGO!やA列車で行こう)を楽しむファン。 |
| SL鉄 | 蒸気機関車(SL)を特に愛好するタイプ。 |
| ジッセ(次世代若手) | 若い世代の鉄道ファンを指す言葉。 |
| ママ鉄・親子鉄 | 子供と一緒に鉄道趣味を楽しむ母親層や親子での鉄道ファン。 |
| プロ鉄 | 鉄道会社に勤務するなど、鉄道を職業とし専門的に関わる人。 |
| 音鉄や模型鉄以外にも多種多様な分野 | 線路を研究する「線路鉄」、配線設備に注目する「配線鉄」など非常に多様な趣味分野がある。 |

こんなに細分化されているなんて知らなかった!
このように、鉄道ファンの趣味や関心は単に写真撮影の「撮り鉄」だけでなく、乗車、音声収集、模型制作、車輌研究、歴史探訪、駅文化、法規研究、さらには食文化(駅弁)やゲームまで幅広く分かれており、それぞれ独自の楽しみ方をしています。
まとめ
今回は『撮り鉄「テモる」の意味や語源とは?マナー違反な専門用語!』について紹介しました。
▶撮り鉄「テモる」の意味
撮り鉄の「テモる」の意味は、撮り鉄が電車を止めたり、緊急停止させる行為を指す俗語です。
▶撮り鉄が問題視される理由
1.線路内への立ち入り
2.撮影目的の危険行為による事故リスク
3.運行妨害による社会的影響
4.マナー違反やトラブルの多発
5.SNSなどによる承認欲求の高まり
▶その他の撮り鉄専門用語・俗語の意味
撮り鉄の専門用語・俗語には多くの独特な言葉が存在し、撮影や鉄道にまつわる状況を簡潔に表現しています。
▶撮り鉄以外の鉄道ファンの種類
鉄道ファンの趣味や関心は単に写真撮影の「撮り鉄」だけでなく、乗車、音声収集、模型制作、車輌研究、歴史探訪、駅文化、法規研究、さらには食文化(駅弁)やゲームまで幅広く分かれており、それぞれ独自の楽しみ方をしています。
最後までご覧いただきありがとうございました!